どうも、なべやんです。
コネを使って、知り合いの小説を書いている人(P.Nは変えてあります)に小説を寄稿して頂きました。
是非お楽しみください~。
コメントで感想聞かせてくださいね。
P.N 闇鍋のふた 作
~プロローグ~
俺は今、二十年前のことを思い返しながらこの文章を書いている。 文章でも絵でも、単なるメモでも日記でもなんでもいい。死ぬまでにあのときのことを形にして、残しておくべきだと思ったのだ。 あのとき、俺はまだ高校一年生だった。 スマートフォンなんてものは存在していないし、当然ながらSNSもない。ガラケー全盛期の時代だ。うちにはパソコンがなかったから、世界のすべてが、自分の見える範囲でしかなかった。 つまり、四方を山に囲まれた、人口が一万人ほどの田舎町。 これが、当時の俺の世界だ。 服を買うにも、本を買うにも、ゲームを買うにも、電車に乗って三十分先の地方都市まで足を運ばなければならなかった。 不便だけど、楽しかった。過ぎ去ってしまったから、そう思うのかもしれないけれど。 そして忘れもしない、高校一年生の春。 入学直後の、四月のことだ。 俺は病気で右目の視力を失った。 失ったのは、視力だけじゃなかった。左目に負荷がかかったことで、自律神経のバランスまでも失ってしまったし、こちらの方が、世界が半分見えなくなることよりも深刻だった。 俺は今まで乗り物酔いなんてしたことがなかったのに、電車に乗って一分で、吐き気に襲われるようになってしまったのだ。 服を買うのも、本を買うのも、ゲームを買うのも難しくなった。なんせ電車に乗れないのだから。 俺は高校に行かなくなった。 高校は、徒歩で十分ほどの場所にある。だから乗り物に乗る必要はない。でも行かなくなった。いじめられたわけじゃない。友達もいる。勉強も楽しい。それでも、学校に行かなくなった。 行けなくなってしまった。 不登校の理由をムリやり言葉にするなら、『自律神経がおかしいから』が一番近いような気がするけど、どうもしっくりこない。もっと意味不明で、もっと根源的な部分にある何かが狂ってしまったような感じだ。 今でもうまく説明できない。 言葉にできないものは、言葉にしないほうがいいのかもしれない。だから話を戻そう。現代のように豊富な暇つぶしがあったわけじゃないから、家にいてもやることがなかった。 そんな俺に母さんが、 「農業をやってみないか」 と言ってきた。 俺の叔母さん――母さんの妹だ。叔母さんが畑や田んぼをやっているので、その手伝いをしてみないか、という話だった。 俺は、二つ返事でOKした。 なんと言っても暇だったし。 小さなころから田植えと稲刈りくらいは手伝ったことがあるけれど、逆に言うなら、それくらいしか農業に触れたことはなかった。 今から二十年前の夏。 まだ、三十度を超えるほどの暑い日が、あまりなかった夏。 俺はしばらく、叔母さんの家に居候することになった。車で一時間ほどの距離にある、田舎町だ。俺の住んでいる町とほとんど変わりがない。強いて言うなら、俺の町よりも標高が高く、山が近い。観光スポットがあまりないから車通りも少ないし、静かで、空気がキレイだ。 母さんが、叔母さんの家まで車で乗せて行ってくれた。一時間も車に乗っているのは、正直しんどかった。俺は睡眠薬を飲んで、寝ることでその一時間を凌いだ。 到着し、車から俺を下ろした母さんは、用事があるとかですぐに帰ってしまった。 そして俺は、叔母さんと再会した。 「お久しぶりです。よろしくお願いします」 小学生のときはよく一緒に遊んでいたけれど、中学になってからは全然会っていなかった。だから距離感が掴めない。 「大きくなったねえ。大樹」 大樹とは、俺の名前だ。 フルネームは百瀬大樹(ももせだいき)。 ちなみに叔母さんの名前は冬木紫乃(ふゆきしの)という。まあ叔母さんとしか呼ばないから、名前を言う機会なんてないけれど。 「前に会ったのって、四年くらい前?」 「はい」 「肩苦しいなあ。もっとこう、ハローとかでいいよ」 叔母さんが笑いながら言った。叔母さんは三十代で、アウトドアが趣味の行動派である。夏は登山、冬はスキーやスノボーで遊んでいる。だからなのか姿勢も良いし、年齢よりも若く見える。のんびり屋でインドア派の俺とは、正反対の性格をしていると思う。 「さあ、立ち話もなんだし、入って入って」 叔母さんが玄関を開けてくれた。 「自分の家だと思ってくつろいでくれたまえ」 「はい」 外見では年季の入っている古風な家って感じだったけど、中は、居間とキッチンがフローリングで、けっこう現代的だった。でも上座式と下座敷、縁側がある。庭には、収穫したお米を貯めておく蔵まであるから、やっぱり家というよりも、立派なお屋敷という言葉の方が近い気がする。 そしてこの広いお屋敷で、俺と叔母さんの二人暮らしが始まった。 俺が住む部屋は六畳の和室で、文机とタンス、木製の本棚以外に、何も調度がなかった。 その日の夜、俺は真新しい布団にもぐって、嗅ぎ慣れない他人の家の匂いに包まれながら、先のことを考えた。 外の闇では、聞いたことのない鳥の鳴き声が、ずっと響いていた。 次の日。 朝早い時間から、大きな山のふもとにある畑で、たくさんの野菜を収穫した。俺の最初の手伝いは、夏野菜の収穫から始まったのだ。 ナスやきゅうり、ぼたごしょう、ピーマン、カボチャ。カボチャが夏野菜だなんて知らなかった。ハロウィンのイメージがあるから、秋の野菜だって思い込んでいた。 小雨の日には、作業着が泥だらけになった。 なんだか懐かしかった。 土に触れていると、心の中のモヤモヤが、全部流れ出ていくような感じがした。自分の中の、何かが良くなる。土は、そんな気にさせてくれたのだ。だから農業は楽しかった。 そうして八月になった。 叔母さんの畑から、ネギが盗まれた。 これがすべての事件の始まりだった。
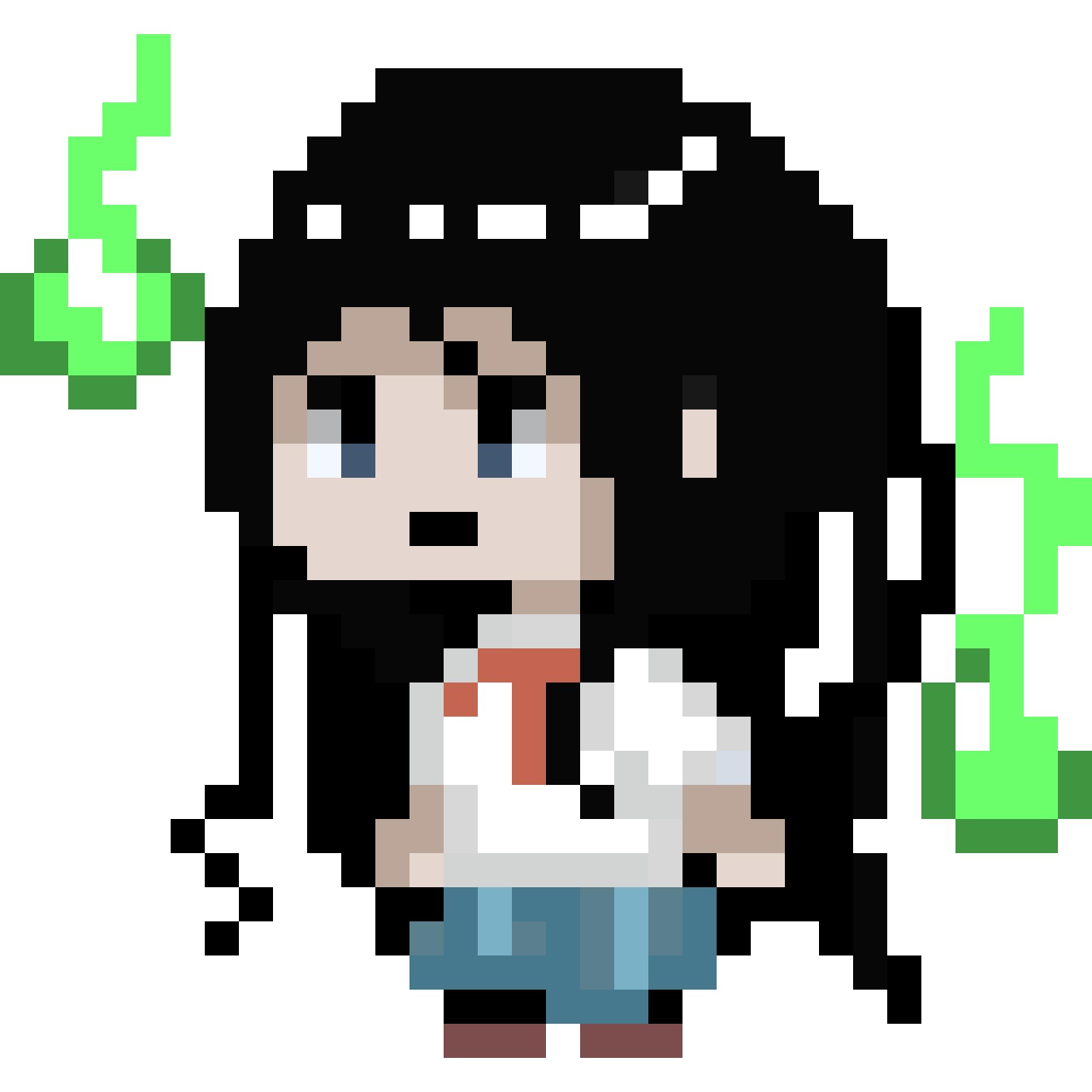


コメント
試しのコメント